「ダイエットしよう!」と思い立ったとき、ついやってしまいがちなのが「極端な食事制限」や「炭水化物抜きダイエット」。
でも、ちょっと待ってください。それ、実は逆効果かもしれません。
この記事では、減量の基本である「摂取カロリーより消費カロリーを多くする」という原則と、やってはいけない間違った食事法についてわかりやすく解説します!
1. 減量の基本は「消費カロリー>摂取カロリー」
人間の体はシンプルで、摂取カロリーが消費カロリーを下回れば体重は減っていきます。
この基本は、どんなダイエット法にも共通する「原理」です。
例えば、1日に2,000kcal使う人が、1,800kcalしか食べなければ、200kcal分は体の脂肪を使ってエネルギーに変えます。これが脂肪燃焼の正体です。
2. 置き換えダイエットや極端な制限はNG!
「1食置き換え」「夜だけスムージー」「炭水化物完全カット」…
こうした方法は、一時的に体重が落ちることもありますが、長期的にはリバウンドや健康被害を引き起こすリスクがあります。
特に炭水化物は脳や筋肉の主要なエネルギー源。抜きすぎると
-
集中力の低下
-
筋肉量の減少(基礎代謝も落ちる)
-
便秘や体調不良
といった症状が出ることも。
炭水化物を抜いたダイエットがなぜ流行ったのか?
「炭水化物を抜いたら一気に体重が減った!」という声、よく聞きますよね。
でも、それは脂肪が落ちたわけではなく、“体内の水分”が抜けただけであるケースが多いです。
炭水化物(特にグリコーゲン)は、体内に1gあたり約3gの水分と一緒に蓄えられます。
つまり、炭水化物を摂らなくなると、この水分が抜けて一時的に体重がストンと減るんです。
これは「痩せた」というより、”水分が抜けただけの“見せかけの減量です。
さらに炭水化物が不足すると、エネルギーが足りずに筋肉を分解してしまうことも…。
結果、筋肉量が減り、基礎代謝も低下→痩せにくい体になってしまうリスクがあります。
3. バランスの良い食事が結果的に一番効率的
体重を落とすには、「無理なく続けられる生活スタイル」が大事です。
-
炭水化物:適量(全体の50〜60%)
-
タンパク質:筋肉を維持するためにしっかり
-
脂質:適度に(オメガ3脂肪酸など良質な脂を選ぶ)
このように、バランスのとれた食事をしながらカロリーコントロールをするのが理想です。
4. 消費カロリーを増やす工夫も大切
摂取量を抑えるだけでなく、「消費カロリーを上げる」ことも大切です。
-
通勤で一駅分多く歩く
-
筋トレで基礎代謝を上げる
-
子どもと一緒に外遊び
など、日常の中にちょっとした運動を取り入れていくと、自然にエネルギー消費量がアップします。
まとめ
減量は「摂取カロリー<消費カロリー」のシンプルな理屈。でも、極端な食事制限は逆効果。
大切なのは“健康的に、バランスよく、無理なく続けること”です。
最後にひとこと(例)
僕自身、過去に炭水化物を抜いてしんどい思いをした経験があります…。
でも、しっかり食べながら地道にやる方が結果的に身体も楽だし、リバウンドしにくい!
「続けられる減量法」こそが、最強のダイエットだと今は思っています。

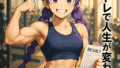

コメント